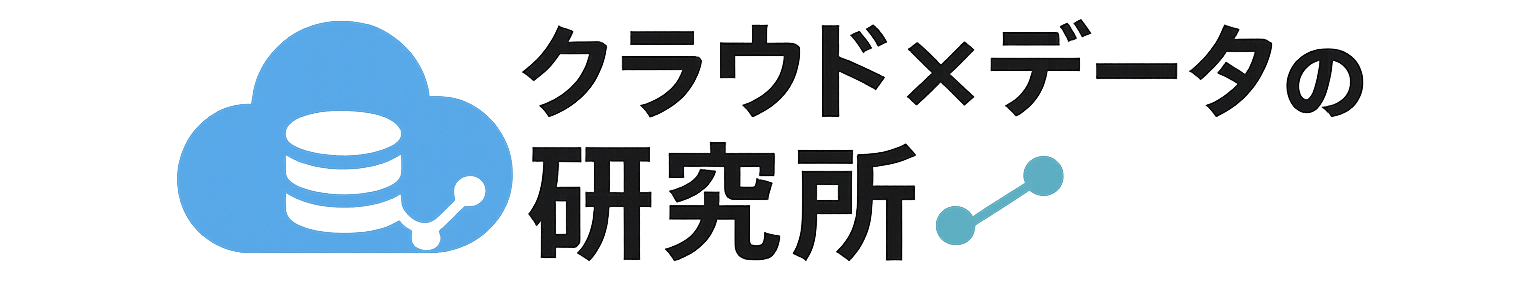こんにちは、データクラウドです!
この記事は、Webマーケティングの最初の一歩「アクセス解析」の全体像をはじめての人でも迷わず動けるレベルでまとめた入門ガイドです。目的・見るべき数字・道具の役割・最初の一手まで、実務の順番どおりに整理します。
Table of Contents
アクセス解析の目的は「正しい打ち手を最短で選ぶ」こと
アクセス解析は、訪問者の行動と属性を数値で把握し、改善の優先順位を決めるための活動です。
「感覚」や「社内の声の大きさ」ではなく、**事実(データ)**でボトルネックを特定して、打ち手を素早く回すのがゴール。きれいなグラフを作ること自体は目的ではありません。
- 例)申し込みが増えない
→ ランディングページの離脱が高いのか、CTAのクリック率が低いのか、フォーム完了率が悪いのかで、直す場所は全く変わります。
代表ツールの役割分担
- Google アナリティクス(GA4):サイト内の行動を計測(閲覧・クリック・スクロール・コンバージョンなど)。
- Google Search Console:検索クエリ、表示回数、平均掲載順位、クリック率(CTR)など検索流入の前段を把握。
- ヒートマップ(Clarity、UserHeat等):ページ内のどこが見られ/触られていないかを可視化。UXの改善判断に最適。
迷ったら「GSCで入口(検索)」「GAで中の動き」「ヒートマップでページ内の詰まり」を見る、が鉄板です。
見るべき基本データ(まずこれだけ)
PV(ページビュー)
どのページが読まれているか。人気・入口候補の把握に使います。PVだけ追うのはNG。次の指標と必ずセットで見ましょう。
UU(ユニークユーザー)
何人来たか。広告・SNS・SEOの全体ボリュームを見る基礎。PVが増えてもUUが変わらないなら「同じ人がたくさん見ているだけ」かもしれません。
セッション
1回の訪問のまとまり。GA4ではイベントベースですが、概念として「訪問単位」を把握しておくと、回遊やCV率の見方が安定します(一般的に30分無操作で区切り)。
直帰率/離脱率
- 直帰率:最初の1ページだけ見て帰った割合(入口のフィット感を示す)。
- 離脱率:各ページを最後に見て離れた割合(導線や次アクションの弱さを示す)。
ランディングページの直帰率、検索クエリ×LPの直帰率は優先的にチェック。
流入経路(チャネル)
検索/SNS/広告/外部リンク/ダイレクト…どこから来たか。集客の打ち手ごとに**質(CVR)と量(UU)**のバランスを見ます。
併せて覚えておきたい用語:
UI/UX(使いやすさ・体験)、フリークエンシー(広告の接触頻度)、発火(イベント発生)、ポータルサイト(ユーザーの入口になるサイト)
まずは「入口」と「出口」を特定する
1) 入口(ランディングページ/主要流入)を洗い出す
- 検索/SNS/広告ごとに最初に踏まれたページを抽出。
- Search Consoleでクエリ×LPのCTRと平均掲載順位を確認。
- 「表示はされるがCTRが低い」=タイトル&メタ説明の見直しが即効性あり。
2) 出口(離脱ページ)を見つける
- PV上位で離脱率の高いページは、まさに改善すべき場所。
- 典型:記事下に関連導線がない、CTAが遠い/弱い、読み込みが遅い、モバイルで折り返しが崩れている。
ボトルネックの見つけ方:分解思考が最短
目標CV数を分解します。
CV数 = LP到達数 × CTAクリック率 × フォーム到達率 × 完了率
どれが弱いかを数字で見極めると、打ち手が自動的に決まります。
- LP到達が少ない → 集客(SEO・SNS・広告)の増強/内部リンク強化
- CTAクリックが低い → ファーストビュー、訴求、CTA配置・テキスト改善
- フォーム到達・完了が低い → 入力項目削減、ステップ分割、ヘルプテキスト、エラー表示改善
よくある“もったいない”落とし穴
- PVだけで判断してしまう
→ CVRや直帰率、スクロール深度、クリックを併せて見ないと改善点は分かりません。 - 期間比較を忘れる
→ 直近7日 vs 直近7〜14日など同曜日比較で季節・曜日のブレを吸収。 - デバイス別に見ない
→ モバイルでのみ直帰が高い=表示速度やレイアウト崩れの可能性大。 - 自己アクセスやステージングを除外していない
→ IP除外やタグ設定を整理。 - 広告の計測漏れ
→ UTMパラメータ(utm_source等)を運用フローに組み込む。 - 支払い完了後のリダイレクトで計測が切れている
→ サンクスページだけでなくイベント発火でCVを拾う設計に。
具体例:読まれているのに離脱が多いページをどう直す?
- 症状:記事AはPV上位、しかし直帰率70%、スクロール50%到達が40%、CTAクリック2%。
- 仮説:
- ファーストビューで価値が伝わらない
- 記事構成が長く、CTAが遠い
- 内部リンクの網が弱い
- 打ち手:
- タイトル・導入文で結論とベネフィットを先出し
- 目次+見出しで答えに最短で辿り着ける構造に変更
- 序盤にも軽いCTA(資料DL/関連記事)を設置
- 本文末に関連3記事の内部リンク
- ヒートマップで非注視エリアの文言・装飾を削除して密度を上げる
- 再計測:1~2週間で直帰率・CTA率・滞在時間・スクロール深度を比較。改善なければ次の仮説に移る(PDCA)。
セグメントで“質”を見る:同じ平均に騙されない
- 流入チャネル別:検索はCVR高いがボリューム不足、SNSはボリューム出るがCVR低い、など。
- デバイス別:モバイルのUX最適化は最優先。
- 新規/リピーター:新規は直帰が高く、リピーターは回遊・CVが高いのが一般的。
- 地域・時間帯:配信や投稿の時間最適化に効く。
- コンテンツタイプ:ブログ/LP/導線ページで役割が違う。役割に合った指標で評価。
ヒートマップで「ページの中の詰まり」を可視化
- スクロール:何%がどこまで読んだか。CTAより上に読了率の崖があるなら、CTA位置か導入の改善が必要。
- クリック:押されて欲しい場所が押されているか。装飾リンクにクリックが集中して肝心のCTAが押されていない、はよくある。
- アテンション:視線が集まる場所とテキストの内容を合わせる。
GA4の実装メモ(最低限)
- 自動計測の拡張計測機能(スクロール、外部クリック等)をON。
- 重要なボタンはイベント名を明示(
click_ctaなど)+パラメータで場所・文言を送る。 - コンバージョン設定はイベント単位で。サンクスページだけに頼らない。
- UTMパラメータを命名規則化(例:
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=lp2025_q3)。
いちばん効く「最初の一手」
- **入口(主要ランディング)と出口(離脱ページ)**をレポート化
- 「読まれているのに離脱が多い」上位5ページを抽出
- それぞれに対して
- タイトル/導入の価値提示を強化
- 見出し骨子を整えて、答えに短距離で届く構成へ
- CTAの手前に価値の証拠(実績・比較・FAQ)を配置
- 関連3記事の内部リンクを上下に
- 表示速度(LCP/CLS)を点検、画像圧縮・不要スクリプト削減
- 2週間後に同曜日比較で再評価(直帰率・CTA率・CVR)
“用語の迷い”をなくす小さな辞書
- PV:ページが読まれた回数(広告のインプレッションとは別)
- UU:訪問した人数の推定
- セッション:1回の訪問のまとまり
- 直帰率/離脱率:入口のミスマッチ/次アクション不足のサイン
- フリークエンシー:広告の接触頻度(同じ人に何回当てたか)
- 発火:イベントが記録されること
- ポータルサイト:多くの人の“入口”になる総合サイト(自社ならカテゴリTOPやハブ記事がポータルの役割)
まとめ:数字が“次の一手”を教えてくれる
アクセス解析は、集客→計測→改善のサイクルを回すための羅針盤です。
- 入口と出口を見つけ、
- 分解思考でボトルネックを特定し、
- 1~2週間のスパンで素早く直して再計測。
この小さなPDCAを、PV上位から順に積み上げれば、確実に成果が伸びます。