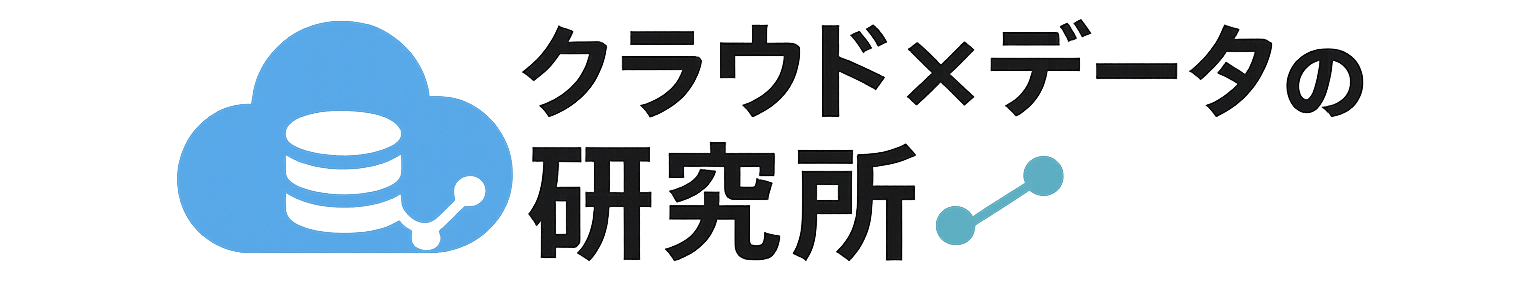Table of Contents
そもそもAPIってなに?
API(エーピーアイ)は Application Programming Interface の略で、日本語では「アプリケーションとアプリケーションをつなぐ窓口」と言えます。
ちょっと難しく聞こえますが、要は「プログラム同士を仲介して便利にしてくれる仕組み」です。
例えば、私たちが普段使うアプリやサービスは一つの会社だけで完結しているわけではなく、他のサービスやデータを呼び出して動いています。
その呼び出しに使われているのがAPIです。
APIのイメージ例:レストランの注文
APIを理解する一番わかりやすい例は「レストランでの注文」です。
- お客さん(アプリ)が「ハンバーグください」と注文する
- ウェイター(API)が注文をキッチン(システム)に伝える
- 出来上がった料理(結果)が返ってくる
お客さんは「どうやって調理しているか」を知らなくても料理を受け取れます。
同じように、開発者は「システムの内部構造を知らなくても」APIを通じて必要なデータや機能を使えるのです。
身近にあるAPIの活用例
- GoogleマップAPI
→ 他のアプリの中に地図を表示したり、住所から経路を自動で検索できる - Twitter API
→ アプリから自動的にツイートを投稿したり、ハッシュタグごとの投稿を取得できる - 決済API
→ ECサイトに簡単かつ安全にクレジットカード決済を組み込める
つまりAPIは、アプリ同士をつなぎ、私たちが便利に使えるようにしてくれている「縁の下の力持ち」なのです。
APIを使うメリット
- 再利用できる:ゼロから作らなくても、既存の仕組みを呼び出せる
- 効率的:短いコードで複雑な処理を実現できる
- 安全性:内部の仕組みを公開せずに外部と連携できる
例えば、自分で天気予報システムを作るよりも、天気APIを呼び出したほうが圧倒的に速く、正確にデータを得られます。
APIとエンジニアの関わり
エンジニアやITに関わる人にとって、APIは「必ず知っておくべき基礎知識」です。
Webアプリを作る人、データを扱う人、モバイルアプリを開発する人――みんなAPIを通じて他のサービスとつながり、価値を作り出します。
特に近年は「データの時代」と言われるように、外部からデータを取ってきて分析やサービス改善に活用する場面が増えています。
APIを理解すれば、それらを効率的に利用して「データ活用型の開発」ができるようになります。
まとめ
- APIはプログラム同士をつなぐ窓口
- レストランの注文のように仲介役
- Googleマップ、Twitter、決済など身近なところで大活躍
- エンジニア全般に必須の知識
「APIを知っているかどうか」で、エンジニアとしてできることの幅は大きく広がります。これからITを学ぶ人にとって、APIは避けて通れない最初のステップなのです。