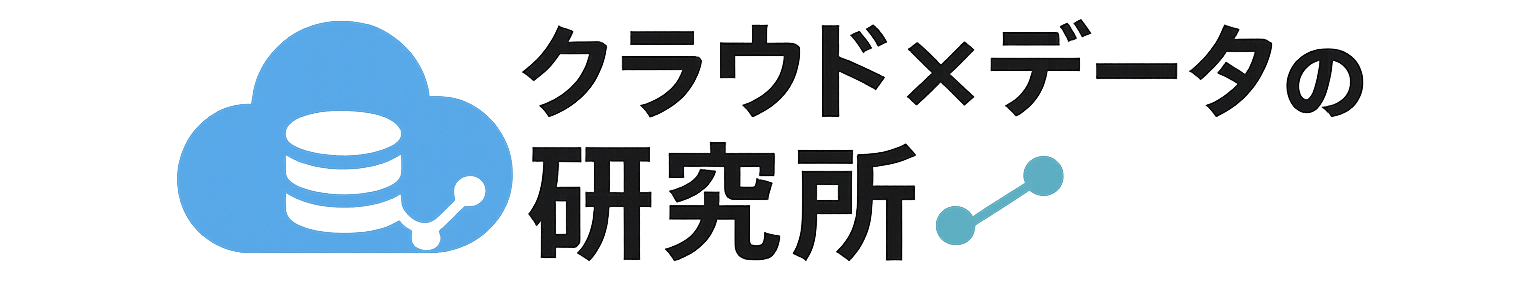「クラウドもAIも聞いたことはあるけれど、どこから手を付ければよいのか分からない」──そんな悩みを抱えるエンジニアは少なくありません。基盤となる技術や開発の考え方、データサイエンスの知識を位置付けて学ぶことで、全体像を理解し、実務に生かせる力が身につきます。本記事ではその整理を試みます。
Table of Contents
基盤技術と開発環境
データ活用の「床」に当たる領域です。Linux・コンテナ・Git・クラウド・IaC・CI/CD は、モデル開発や分析以前に「再現性」「可搬性」「セキュリティ」を担保するための基礎体力になります。これらが整っていないと、データサイエンスの成果物は本番で再現できず、運用に乗りません。「早く・安全に・同じものをどこでも動かせる」環境づくりが、全ての価値創出の前提です。
Linux/UNIX
概要: Linuxは多くのサーバやクラウド環境で標準的に使われるOSです。コマンドラインでの操作に慣れておくことで環境構築やログ確認をスムーズに行えます。例えば、Linuxの基本資格であるLPICレベル1程度の知識があれば、環境操作で「どのコマンドを使えばよいか分からず時間を浪費する」ことが減りますavinton.com。
データ基盤での位置づけ: データエンジニアリングでは、サーバ上でETLバッチを実行したり、コンテナをデプロイしたりする際にLinux環境を扱う場面が多々あります。Linuxのファイルシステム操作、プロセス管理、ネットワーク設定などの知識は、データ基盤の土台となるインフラ基盤スキルの一部です
。
実務での必要性: 実務では、リモートサーバにSSH接続してログを調べたり、Cronでバッチジョブをスケジュールしたり、Hadoop/Sparkクラスタなど大規模データ処理基盤を構築・運用する際にもLinuxコマンドを駆使します。Linuxの知識があると、環境トラブル対応やサーバ資源の監視が的確に行えるため、データ基盤の安定運用に欠かせません。
Docker/コンテナ仮想化技術
概要: Dockerはコンテナ型の仮想化技術で、アプリケーション実行環境をパッケージ化して再現性高くデプロイできます。コンテナを用いることで、他の環境へシステムを丸ごと複製しやすくなりますavinton.com。これにより「自分のPCで動くのに本番で動かない」といった問題を解消し、環境差異をなくすことができます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤においても、ETL処理や機械学習モデルのサービス化にDockerがよく使われます。コンテナにより依存関係ごとアプリケーションを封じ込めることで、開発・本番環境間で動作を一致させたり、Kubernetesなどでのコンテナオーケストレーションに乗せてスケーラブルにバッチやAPIを運用できます。またCI/CDパイプライン上でテスト環境を構築する際にもDockerコンテナが利用されます。
実務での必要性: 実務では、チームメンバー全員が同一のDockerイメージを使って開発することで「誰の環境でも同じ結果が得られる」状態を作りますavinton.com。例えばデータクレンジングのスクリプトやJupyter Notebook環境をDocker化し共有すれば、環境構築の手間を減らし、オンボーディングも容易になります。さらに、本番にデータ処理アプリケーションをデプロイする際もDockerイメージとして提供することで、クラウド上でスムーズに稼働させることができます。コンテナ技術はデータ基盤の移植性・拡張性に直結するため、習熟しておくことが望ましいです。
Git/Github
概要: Gitはソースコードのバージョン管理システムで、変更履歴を記録しチームでの開発を円滑にします。他の開発者が読んだときにコードの意味を理解でき、修正を管理できることが重要です。ソフトウェア開発者やデータエンジニアにとって、Gitのようなバージョン管理ツールは必須であり、実務ではSVNなどよりGitが事実上標準となっています。
データ基盤での位置づけ: データ基盤においても、ETLスクリプトやSQLクエリ、インフラ構成コード(後述のIaC)やドキュメントなど、あらゆる成果物をGitで管理します。これにより、誰がいつどの変更を加えたか追跡でき、問題発生時に原因を特定しやすくなります。またGitHubやGitLabを用いてコードレビューを実施することで、コードの品質向上とナレッジ共有を図ります。
実務での必要性: 実務では、Gitを使ったブランチ運用(GitフローやGitHubフロー)により、安全に機能追加やバグ修正を進めます。データパイプラインのコードや分析用SQLも、小さな変更でも必ずGitにコミット&プルリクエストを経てレビュー・マージする運用が一般的です。これにより、コードの「単一の信頼できる情報源」を維持し、開発チーム全員が最新のコードを共有できます。Gitに不慣れだとチーム開発に参加できないほど重要なスキルなので、基本的な使い方からブランチモデルまで習得が必要です。
クラウド技術/AWS
概要: AWS(Amazon Web Services)は代表的なクラウドサービス群で、計算・ストレージ・データベースなど様々な機能をオンデマンドで利用できます。現在クラウドへの移行が主流となっており、AWSはクラウドプラットフォームの中でも群を抜いて普及しています。EC2によるサーバ提供やS3によるストレージ、Lambdaによるサーバレス実行環境など、多彩なサービスを持ちます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤では、オンプレミス環境からクラウド環境へ移行するケースが多く、AWS上でデータレイクやデータウェアハウスを構築・運用することが一般的です。例えばデータ蓄積にS3、データウェアハウスにRedshift、ETLにGlueやLambda、分析基盤にAthenaやEMRなど、AWSの各サービスを組み合わせてエンドツーエンドのデータパイプラインを構築できます。AWSの基本サービス(EC2やS3、IAMなど)への習熟はクラウド理解の土台として重要です。
実務での必要性: 実務では、AWS上で新たなデータ基盤プロジェクトを立ち上げる場面が多いです。例えばオンプレのデータをAWSに移行し、S3にデータレイクを作り、Glueでデータカタログを整備し、Redshiftで分析用データマートを構築するといったケースです。また、AWSのIAMで適切なアクセス制御を設計することもセキュリティ上不可欠です。クラウド特有のコスト管理(例: 不要リソースの停止)やスケーラビリティ確保(Auto Scalingの設定など)も日常業務となるため、AWSの知識と運用経験が実務で強く求められますavinton.com。さらに他クラウド(GCPやAzure)でも基本概念は共通するため、AWSの理解はクラウド全般の理解にもつながります。
IaC (Infrastructure as Code)
概要: IaCは「Infrastructure as Code」の略で、サーバやネットワークなどインフラ構成をコードで記述し、自動構築・管理する手法です。代表的なツールにTerraformやAWS CloudFormation、AWS CDKなどがあります。インフラ構築の“コード化”により、手作業の設定ミスを減らしつつ、構成をバージョン管理して再現性を高められます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤では、多数のサーバやサービス(データベース、キューバ、ETLサーバなど)を組み合わせます。IaCを用いることで、これら構成をスクリプト化して一貫した環境を用意できます。例えばTerraformでVPCやEC2、RDS、Redshiftをコードで定義すれば、同じ構成を開発・検証・本番で再現可能です。またGitでIaCコードを管理し、コードレビューやCI/CDでの自動適用も可能です。IaCにより**「本番環境だけ設定が違う」といった問題を防止**し、環境差異なくインフラを管理できます。
実務での必要性: 実務では、インフラ構築案件でTerraformテンプレートを作成したり、既存環境をコード化して“見える化”することが求められます。特にクラウド上のリソースをIaCで管理すると、設定変更をコード差分で追跡でき、レビューによる統制も効きます。また前述のとおり人為ミスの低減につながるため、セキュリティ強化策としてもIaCが活用されますbook.st-hakky.com(設定の一貫性確保とヒューマンエラー防止)。インフラエンジニアだけでなくデータエンジニアも、TerraformやAWS CDKのコードを読める・書けることが、モダンなデータ基盤構築では重要になっています。
CI/CD
概要: CI/CDはContinuous Integration/Continuous Delivery(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の略で、コードのビルド・テスト・デプロイを自動化するプロセス全般を指します。データ基盤の変更を自動ビルドし、テスト・リリースまで行う仕組みとも定義されます。具体的には、Gitにコードがマージされたら自動で単体テストやコードチェックが走り、問題なければ本番環境にデプロイまで実施する、といったパイプラインを構築します。
データ基盤での位置づけ: データ基盤開発でもCI/CDは品質と開発速度を両立する鍵です。例えば、ETLの変換ロジック(SQLやPythonコード)に対して自動テストを用意し、CI環境(GitHub ActionsやJenkinsなど)で常に検証するようにしますrakus-partners.co.jprakus-partners.co.jp。これによってデータ変換ロジックの改変で不具合が混入するのを防ぎます。また、CI/CDにより分析クエリやダッシュボード定義の変更も自動デプロイできれば、分析環境のアップデートが迅速になります。
実務での必要性: 実務では、Gitのプルリクエスト作成と同時にCIでユニットテストやLint(静的コード解析)を走らせ、レビューアに問題点を早期に知らせます。ビッグデータ処理のコードでも、小規模データで動作検証するテストを仕込み、これをCIで毎回実行します。またCDにより、本番データベースへのスキーマ変更SQLを自動適用したり、Airflowなどのワークフロー定義を自動更新したりも可能です。「人の手によるデプロイ作業」を減らし信頼性を高めるために、CI/CDパイプラインの構築スキルが求められます。エンジニアはこれらツールの設定(YAML等)に慣れておく必要があります。
開発と品質
ビジネス価値は「動くもの」として届いて初めて評価されます。リーダブルコード、Webアプリ開発、Webセキュリティは、データやモデルを「プロダクトに落とし込む表現力」と「守る力」です。読みやすいコードは変更容易性を高め、堅牢なWeb実装は攻撃や誤用から価値を守ります。データ活用の「出口の品質」を担保するための必須要素です。
コーディング技術/リーダブルコード
概要: 「リーダブルコード」とは、他人が読んだ時に理解にかかる時間を短くできるコードのことですqiita.com。単に動作するコードではなく、意図や構造が明確で保守しやすいコードを書くための考え方・技術を指します。具体的には、変数・関数名を見ただけで役割がわかるようにする、一目で処理の流れが追えるようレイアウトやコメントを工夫する、冗長や複雑すぎるロジックを避ける等の実践があります。
データ基盤での位置づけ: データエンジニアリングでは、SQLクエリやスクリプト、設定ファイルなどチームで扱うコードが多岐にわたります。リーダブルコードのスキルがあると、例えば長大なSQLでもサブクエリに意味のあるエイリアス名を付けて可読性を上げたり、データパイプラインのジョブ名を見ただけで処理内容が想像できるよう命名規則を統一したりできます。これは属人化の防止に直結し、他のメンバーが安心してコードを引き継いだりレビューしたりできる状況を作ります。
実務での必要性: 実務のチーム開発では、可読性の低いコードはバグの温床になり、修正にも時間がかかります。例えばデータ変換処理のSQLで、意味のない略語だらけのカラム名・テーブル名を使っていると、後から見た人が理解に苦労します。それを避けるため、チーム内でコードスタイルガイドを定め「6か月後の自分が見ても一瞬で理解できるコード」を目指すべきだとされていますqiita.com。リーダブルコードの原則を念頭に置けば、結果としてプロジェクト全体の生産性とコード品質が向上します。実務者は書籍『リーダブルコード』等で示されるテクニックを学び、日々のコーディングに取り入れることが望ましいでしょう。
Webアプリケーション開発
概要: Webアプリケーション基礎とは、インターネットやHTTPの仕組み、サーバとブラウザの通信、RESTful APIなどWeb技術全般の基本知識です。具体的には、HTTPメソッドやステータスコードの意味、クッキーやセッションの概念、JSONやXMLといったデータフォーマット、そしてサーバサイドフレームワーク・フロントエンドの役割分担などが含まれます。現代のソフトウェア開発ではWeb標準技術が幅広く使われているため、HTTPやDNSなどの基礎知識はインフラ基礎スキルの一部とされています。
データ基盤での位置づけ: 一見データ基盤とWebは別領域に思えますが、実際には密接に関わります。例えばデータ収集ではWeb APIからJSONデータを取得するケースが多く、APIの認証やレスポンス解析のためにHTTPの理解が必要です。また、分析結果を提供する際にWebダッシュボードや社内ポータルを作成する場合、その裏側でWebアプリケーションを構築します。機械学習モデルをWebサービスとして提供(AI API化)するときも、FlaskやFastAPIといったWebフレームワーク知識が必要です。つまりデータの入出口はしばしばWebであり、その基本を押さえておくことが重要です。
実務での必要性: 実務では、データエンジニアがREST API経由で第三者提供データを取得して自社データベースに蓄える、といった業務がよくあります。その際にHTTPのリクエストヘッダ設定や、OAuth認証の手順を理解していないと実装に手間取ります。また、社内向けのデータ可視化Webアプリ(例えばPythonのDashやStreamlitを使う場合)を開発することもあります。そうした際、基本的なクライアント・サーバモデルの理解や、セキュアな通信(HTTPS)の設定など、Webの基礎知識が役立ちます。Webアプリ基礎を知ることで、データ活用の成果物をエンドユーザーに届ける最終段階まで対応できるエンジニアになれるでしょう。
Webセキュリティ
概要: Webセキュリティは、WebアプリやWeb APIを脅威から防護するための知識・対策です。代表的な脆弱性としてSQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティング(XSS)などがあり、これらを悪用されると機密データ漏洩や改ざん等の深刻な被害につながります。他にもCSRF(サイト間リクエスト偽造)、クリックジャッキング、OSコマンドインジェクションなど多岐にわたる脅威があります。Webセキュリティでは、入力値の適切なサニタイズやエスケープ、認証・セッション管理の堅牢化、暗号通信(HTTPS)の利用など、多面的な対策を講じます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤でもWebセキュリティは無縁ではありません。例えば社内外に提供するデータ可視化ダッシュボードや、機械学習モデルのAPIエンドポイントが存在すれば、それらはWebアプリケーションとしてセキュリティ対策が必要です。データ基盤における認可(アクセス制御)も広義のセキュリティ事項であり、扱うデータの機密度に応じて利用者権限を設計します。またクラウド上でデータを扱う場合、APIキーや秘密鍵の安全な管理もWebセキュリティと密接です。安全なWebアプリケーションの作り方を理解することは、データプラットフォーム全体の信頼性を守ることにつながります。
実務での必要性: 実務では、例えばデータ分析用に提供した社内Webサービスが認証不備で他人に見られてしまった、ということが起きないようにしなければなりません。開発時にはOWASP Top 10などを参考に、自分のアプリがこれら典型的脆弱性に対処できているか確認しますipa.go.jp。具体的には、SQLインジェクションを防ぐためにプリペアドステートメントを使う、XSS対策としてHTMLエスケープを徹底する、セッションIDは推測困難にしてHTTPSで送受信する、などです。また、クラウド環境の設定ミスによるデータ公開リスクもあるため、設定のレビューや定期的なセキュリティ監査も欠かせませんbook.st-hakky.com。データエンジニアであっても基本的なセキュリティ知識を持ち、実装やインフラ設定に反映させることが重要です。
データベースとデータ基盤
DB/SQL/モデリング/DWH/dbt/BI/データマネジメントは、データを「正しく蓄え、整え、届ける血流」です。スキーマ設計と品質管理が甘いと、どれだけ優れたモデルも信頼されません。「単一の真実」をつくる設計と、変換・可視化までの一貫したフローが、日々の意思決定を支えます。
データモデリング(リレーショナル/ディメンショナル)
概要: データモデリングとは、業務要件に合わせてデータの構造(モデル)を設計することです。代表的な手法にリレーショナルモデルとディメンショナルモデルがあります。リレーショナルモデルではエンティティ(表)間の関係を正規化しつつ整理し、データの一貫性と無駄のない構造を目指します。一方、ディメンショナルモデルは分析に最適化されたモデルで、中心の事実(ファクト)とその切り口となる次元(ディメンション)から成りますsap.com。例えば、「売上額」という定量データをファクトとし、「商品ID」「単価」「取引日」などのディメンションでその文脈を表現しますsap.com。ディメンショナルモデルではファクトをまとめたスター型スキーマを採用することでクエリを高速化できます(重複よりも性能を優先)。
データ基盤での位置づけ: データ基盤設計では、トランザクション処理向けにはリレーショナルモデリングを、分析向けデータマートにはディメンショナルモデリングを使うのが一般的です。例えば業務システムのOLTPデータベースは第3正規形まで正規化して更新効率と整合性を保ちます。一方でBI用のデータマートは売上や顧客といったビジネスプロセス単位でファクトとディメンションを設計し(スター型スキーマ)、ユーザー部門が理解しやすく高速に集計できる構造にしますintegrate.iointegrate.io。データモデリングスキルはデータエンジニアにとって基盤的能力であり、適切なモデル設計なくしてはデータ活用が非効率になったり、後工程(BI分析や機械学習)に支障をきたします。
実務での必要性: 実務では、たとえば新規サービスのデータベース設計時に、エンティティ間の関係をER図で整理しつつ正規化/非正規化のバランスを判断します。さらにデータ分析用に、既存DBから定期抽出する形でデータウェアハウス用スキーマを新たに設計することもあります。その際、**「どの粒度でファクトテーブルを設け、どの軸をディメンションとして切るか」**といったディメンショナルモデリングの腕が試されますintegrate.io。例えば日次・商品別売上集計を高速に行うために、売上明細テーブルと商品・日付ディメンションを適切に設計する、といった具合です。モデリングが不適切だと、後々クエリが複雑化したりパフォーマンス問題が起きるため、実務では要件ヒアリングを踏まえ丁寧にモデル設計を行います。またモデル設計はチーム内外の共通言語にもなるため、その説明・文書化も含めたスキルが重要です。
DB(データベース)
概要: DBとはデータを組織的に蓄積・管理するシステムです。代表的なリレーショナルデータベースは行と列からなるテーブル形式でデータを保持し、SQLで操作します。一方NoSQL(非リレーショナル)DBはキーバリュー型やドキュメント型など多様なモデルがあり、用途に応じて柔軟です。データベース技術は30年以上前から存在し、今後も不可欠とされる基盤技術であり、開発者はSQLに加えて正規化やテーブル設計などの重要概念にも通じておく必要があります。
データ基盤での位置づけ: データ基盤では様々なDBが登場します。例えばオンラインサービスのトランザクションデータはリレーショナルDB(OLTP系)に蓄積されますし、集計や分析用途にはデータウェアハウス(これも広義には専用のリレーショナルDB)が用いられます。また大規模データやログはスケーラビリティ重視でNoSQLに入れる場合もあります。データベース関連スキル(SQLやデータモデリングなど)はデータエンジニアの必須スキル領域と位置付けられています。各種DBの特徴を理解し、シーンに応じ適切なものを選択・設計する能力が求められます。
実務での必要性: 実務では、まず既存システムのDB(例:MySQL/PostgreSQLなど)のスキーマを把握し、必要に応じてクエリ最適化やインデックス設計を行います。また、新規にデータマートを構築する際は、分析しやすいスキーマをデータモデリングして実装します。運用中には、DBのパフォーマンス監視や容量管理、バックアップ計画の立案も必要です。さらに最近では、データエンジニアがNoSQL(MongoDBやCassandraなど)や分散データストア(Hadoop/Hiveなど)の運用に携わることも増えています。データを安心・効率的に蓄えるDBの知識は、データ活用の土台として非常に重要です。
SQL基礎/応用
概要: SQL(Structured Query Language)はリレーショナルDBを操作するための問い合わせ言語です。データの検索(SELECT文)、抽出条件の指定、集計や結合、更新・削除などを宣言的に記述できます。SQLは非常に強力な言語で、複雑なデータ分析でもわずか数行のコードで実現できることがあります。基礎的なSELECT文から、ウィンドウ関数・サブクエリ・ピボット・再帰クエリなど高度な機能まで習熟することで、大量データから自在に洞察を得られるようになります。
データ基盤での位置づけ: SQLはデータ基盤の至る所で登場します。データクレンジングや集計処理はETLツール上でSQLを書く場合が多いですし、データアナリストもBIツールで直接SQLクエリを書くことがあります。データウェアハウス製品(BigQuery, Redshift, Snowflake等)はSQLで操作する前提です。データパイプラインの開発者には、高度なSQLクエリの作成やパフォーマンスチューニングのスキルも求められますrakus-partners.co.jp。例えばインデックスの仕組みを理解してクエリを書けば、応答速度が大幅に向上します。SQLはデータエンジニアのみならずデータに関わる全職種で重要なコミュニケーション手段とも言えます。
実務での必要性: 実務では、テラバイト級のテーブルから必要な指標を算出するようなクエリを書くこともあります。その際、効率の悪いSQLだと処理に何時間もかかったり、最悪タイムアウトすることもあります。したがって、実務者はSQLのパフォーマンス特性(結合順序や集計方法による違い)を理解し、チューニングやリファクタができなければなりません。また、複雑な要求に応えるためウィンドウ関数やCTE(共通テーブル式)を駆使する場面も多いです。SQLは一見シンプルですが奥が深く、応用力は経験に比例します。常にクエリの結果検証を行い、正確さと効率を両立するSQLスキルを磨くことが大切です。
DW(データウェアハウス)構築
概要: DW(データウェアハウス)構築は、企業内外の様々なデータソースからデータを収集・統合し、分析可能な形で蓄積するシステムを設計・実装することです。その要素には、データインジェスト(取り込み)、バッチ処理(定期的な変換・集計)、そしてセキュリティ対策が含まれます。データインジェストでは、データベースやログ、APIなどから一定間隔でデータをDWにロードします。バッチ処理では、例えば毎晩決まった時刻にその日のデータを集計してテーブルを更新する、といった定期処理を設計します。セキュリティは、DWに集約された大量の機密データを守るためのアクセス制御や暗号化、監査ログの整備を指します。特にロールベースのアクセス制御(RBAC)によってユーザごとにアクセス権限を適切に設定することが重要です。
データ基盤での位置づけ: データウェアハウスは企業の「単一の真実の源泉(Single Source of Truth)」として機能しsap.com、DXやBIの基盤となります。データ基盤エンジニアは、各種システム(ERPやCRM、IoTデバイス、外部データなど)からDWへのデータフローを設計し、必要に応じてETLまたはELTパイプラインを構築します。バッチ処理は、売上集計や顧客分析用のスナップショットを定期生成するなど、DW内でのデータ整形に用います。またセキュリティの観点では、DWはしばしば全社の重要データを集中させるため、不正アクセス防止やデータマスキング、監査ログ出力などガバナンス機能の実装が欠かせませんbook.st-hakky.com。DW構築スキルはすなわち、大規模データを安全かつ効率的に取り込み・保持・提供するスキルと言えます。
実務での必要性: 実務において、例えば「現行の基幹DB・Excelで点在するデータを一箇所に集め、分析できるようにしたい」という要件に応えるのがDW構築です。エンジニアは、データソースごとにインジェスト方法(JDBC接続やファイルバッチ、ストリーミングなど)を選定し、ワークフローを開発します。夜間バッチのスケジュールを調整し、依存関係に従ってジョブ実行順序を管理します。セキュリティ面では、特に個人情報や機密データを含む場合は暗号化を施します(保存時暗号化により万一ストレージが流出しても内容を保護book.st-hakky.com)。アクセス権は「部署AはテーブルXのみ閲覧可」等、RBAC設定を行いbook.st-hakky.com、さらに定期的にアクセスログや脆弱性診断を実施して安全性を検証します。DW構築は幅広い工程を伴いますが、この一連のスキルにより企業データを価値ある形で蓄積・活用できるようになります。
dbt / データ変換ツール
概要: dbt(data build tool)はデータ基盤におけるETLの「T(Transform)」部分を担うオープンソースツールです。分析用データを作成するSQLクエリをコードとして管理し、依存関係に応じて自動的に実行順序を制御したり、テストやドキュメント生成を行ったりする機能を備えています。要するに、データ版のGitHubのように変換処理をコードで共有・管理し、ソフトウェア開発のベストプラクティス(バージョン管理・自動テスト・リリース管理など)をデータ変換に持ち込むものですzenn.dev。誰でもSQLさえ書ければデータパイプラインを構築・運用できる点が革新的です。
データ基盤での位置づけ: モダンなデータスタックでは、まず元データをデータレイクやDWHにロード(ELTの「EL」部分)し、その後dbtでクレンジング・集計・結合などの変換をSQLで行いますzenn.dev。dbtはSQLモジュール(モデル)の依存関係を解析して最適な実行順序を決定し、例えば「売上集計テーブル」は「売上明細テーブル」と「商品マスタ」が変換済みでないと作られない、といった順序を自動で保証します。さらにYAMLでテスト(NOT NULL制約や一意性チェック等)を書けばデータ品質チェックを自動化し、ドキュメントも生成してくれますzenn.dev。これにより、従来属人的だった変換処理をチームで管理しやすくなり、データ基盤の変換プロセスの信頼性が飛躍的に向上します。
実務での必要性: 実務では、例えば手作業で書かれていた多数のSQL変換をdbtプロジェクトに移行し、Gitで管理することで変更履歴を追えるようにするといった活用がされます。またdbt Cloudなどを使えばスケジューリングやモニタリングも一元化できます。ある企業では、データマート構築にdbtを導入した結果、エンジニア以外のアナリストも自分で必要な派生テーブルを作成できるようになった例もありますzenn.dev。これはSQL知識だけでデータモデルを作れるdbtの利点です。加えて、モデル間のドキュメントやテスト整備によりデータの信頼性が高まり、組織全体で安心してデータ活用が進むようになりますzenn.devzenn.dev。現代のデータエンジニアにはdbt活用経験が求められるケースも増えており、データ変換プロセスをコードとして扱うスキルは必須になりつつあります。
Snowflake(クラウドDWHプラットフォーム)
Snowflake は、クラウドネイティブに設計されたデータウェアハウス(DWH)です。特徴は「ストレージとコンピュートの分離」で、柔軟なスケーリングと高いコスト効率を実現します。SQL ベースで利用できるため既存のデータアナリストにも親和性が高く、BI ツールや機械学習基盤と組み合わせた「モダンデータスタック」の中心的存在となっています。
Databricks(レイクハウスプラットフォーム)
Databricks は、データレイクと DWH の強みを統合した「レイクハウス」アーキテクチャを提供するプラットフォームです。基盤となる Delta Lake により、データを信頼性の高いテーブル形式で扱えるのが特徴です。さらに Spark による大規模分散処理や MLflow による機械学習の実験管理など、データエンジニアリングからデータサイエンス・AI 活用までを一貫してサポートします。
BI(Business Intelligence)
概要: BI(Business Intelligence)とは、企業内の様々なデータを集約・可視化・分析して、経営に役立つ洞察を得ること、またそのためのツール群を指します。BIツール(例: Tableau, Power BI, Lookerなど)はデータをグラフやダッシュボードにまとめ、非エンジニアでもデータに基づいた意思決定を行えるよう支援します。BIではドラッグ&ドロップで集計レポートを作成したり、定期的にレポートを自動配信したりする機能があります。要するに、データ分析の民主化を実現するソフトウェアとプロセス全般です。
データ基盤での位置づけ: データ基盤が整備された後、その上で価値を生み出すのがBI層です。データウェアハウスに蓄えられた「単一の真実」のデータから、BIツールでダッシュボードを構築すれば、経営・現場問わず必要な指標をリアルタイムに確認できます。例えば売上、在庫、人事データなどを横断して可視化し、組織のKPI管理に使うことがBIの典型です。データエンジニアはBI担当者と協働し、分析しやすいデータマート設計やクエリ最適化を行います。またBIツール自体の管理(ユーザー権限設定やデータソース接続設定)もデータ基盤チームの役割となることがあります。BIはデータ戦略の「最後の一歩」であり、ここで有効なアウトプットを出してこそデータ活用が成果に繋がります。
実務での必要性: 実務では、経営層向けのダッシュボード作成や、日々の業務改善に役立つ可視化レポートの提供が求められます。BIスキルとしては、適切なグラフ選択、見やすいレイアウト設計、ユーザーが対話的にフィルタ操作できるUI設計などが挙げられます。例えば売上分析ダッシュボードで、全社→部門→個人とドリルダウンできるように作れば、利用者は多角的にデータを閲覧できます。エンジニアはデータモデル側でわかりやすい命名や単位揃えを行い、利用者が迷わず指標を把握できるよう支援しますsap.com。BIの目的は「正確で一貫性のあるデータに基づき迅速に意思決定すること」sap.comなので、その実現にはツール操作スキルだけでなく、業務理解とコミュニケーション能力も重要です。最終的に、BIスキルはデータから価値を引き出しビジネスに貢献する要となるでしょう。
データマネジメント
概要: データマネジメントは、企業内のデータ資産を効果的に管理・活用するための総合的な取り組みを指します。データガバナンス(方針策定・監督)によって示された方向性に基づき、日々の具体的なデータ活用活動全般を実践するものがデータマネジメントです。その範囲は、データ品質管理(品質基準の設定とモニタリング)、メタデータ管理(データ辞書やカタログの整備)、マスタデータ管理(企業内の主要なデータを一元管理)、データセキュリティとプライバシー対応(アクセス制御や個人情報保護)、データライフサイクル管理(生成から廃棄までのフロー設計)、組織体制(データオーナーやスチュワードの任命)など非常に広範囲です。要するに、データに関する人・プロセス・技術全てを統合的に扱う枠組みです。
データ基盤での位置づけ: データ基盤はデータマネジメントの技術的中核ですが、これをうまく機能させるには周辺の管理プロセスが不可欠です。例えば、せっかく立派なデータレイクを構築してもデータ品質が信頼できなければ誰も使いません。そこでデータマネジメントの一環として、各データセットの品質指標(欠損率や整合性)を定義・測定し、問題があれば改善計画を立てます。またメタデータ管理では、データカタログツールにテーブルやカラムの説明、更新頻度、問い合わせ先担当者などを記載し、社内の誰もがデータの意味を調べられるようにします。データガバナンスの観点では、データ利活用のルール(例えば個人情報は特定部署のみアクセス可など)を定め、違反がないか監督します。データマネジメントがしっかりしている組織ほど、データ基盤が有効に活用されデータ駆動文化が根付くと言われています。
実務での必要性: 実務では、データ戦略を推進する部署がデータマネジメントのロードマップを描き、具体策をデータエンジニアやアナリストと共に実行していくケースが増えています。例えば「データ品質向上プロジェクト」と銘打って、主要KPIの計算ロジックを一本化する、異なるシステム間でマスタを統合する、といった取組を行います。また、法規制対応もデータマネジメントの重要テーマです。GDPRや日本の個人情報保護法に対応するため、データの匿名化や利用目的管理のプロセスを整える必要がありますbook.st-hakky.com。データエンジニアも、こうした活動に技術面から貢献します(例えば特定の個人データを容易に抽出できるようタグ付け・暗号化する仕組みを作る等)。データは戦略資産と位置づけられる時代、データマネジメントのスキルはエンジニアにとっても経営貢献度の高いスキルと言えるでしょう。
AI・データサイエンス
統計・機械学習・ML/AIアプリ開発は、データから「予測」と「自動化」を生み出す中核です。統計は仮説検証の土台、MLはパターン抽出のエンジン、AIアプリは価値を届ける仕組みです。ここで生まれるアウトプットは、上流のデータ基盤が支え、下流のアプリと運用が届けます。「再現性」「説明可能性」「運用容易性」を意識した設計が成果の持続性を決めます。
AIアプリケーション開発
概要: AIアプリケーション開発とは、機械学習や深層学習モデルを組み込んだアプリケーションを設計・実装することです。モデルの構築自体のみならず、モデルをサービスとして提供するためのソフトウェア開発全般を指します。近年は生成AIの発展により、個人や中小企業でもAIアプリに取り組みやすくなり、多くの企業が業務効率化や顧客体験向上の切り札として注目する分野で。AIアプリ開発では、Pythonなどでモデルを実装し、推論APIやバッチ推論システムに統合するスキルが求められます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤におけるAI活用の最終形が、AIアプリケーションの展開です。例えばデータ基盤で蓄積・加工したデータを使って予測モデルを構築し、そのモデルをWebサービスとして提供する場合、データパイプラインとアプリ開発の両方の知識が必要になります。AIアプリ開発にはモデルの入出力インタフェース設計、リアルタイム推論かバッチ推論かの検討、モデル更新の仕組みなど、データサイエンスとアプリケーション開発の橋渡し役となる視点が求められます。言い換えれば、データ基盤で作った成果(モデル)を実際の業務フローに組み込む工程がAIアプリ開発と言えます。
実務での必要性: 実務では、例えばチャットボットやレコメンドエンジン、需要予測システムなどのAI機能を持つアプリを開発する場面があります。その際、モデルの精度向上だけでなく、エンドユーザーが利用できる形で素早く実装する俊敏性(アジャイル開発)が重要です。またモデルを本番環境にデプロイし運用するMLOpsの考え方も必要不可欠ですqiita.com。具体的には、モデルをコンテナ化してクラウドにデプロイし、API経由で予測結果を返せるようにする、モデルのバージョン管理や監視(精度劣化の検知など)を行う、といった開発運用プロセスを整備します。AIアプリ開発スキルを持つことで、単なる分析に留まらずビジネス現場で使われるソリューションを完結に提供できるエンジニアになれます。
統計/数学
概要: 統計学はデータを解析してそこに潜む規則性や差異を客観的に評価する学問で、データ活用の理論的基盤です。統計の基本には、平均・中央値・分散・標準偏差といった記述統計から、母集団の特性を推定する推測統計(例: 区間推定、仮説検定)まで幅広い概念があります。データを適切に扱い分析するには統計知識が必須でありskillupai.com、統計リテラシーが低いと分析結果の誤解釈や誤用につながります。例えば「平均」と「中央値」の違いを理解してデータのばらつきを把握したり、A/Bテストで統計的有意差を検定してビジネス施策の効果を判断したりします。さらに相関・回帰分析、多変量解析、時系列解析など応用的な手法も統計の応用範囲です。
データ基盤での位置づけ: データ基盤に統計学は直接組み込まれるわけではありませんが、その上でデータ分析・機械学習を正しく行うための前提教養として極めて重要です。データ品質の評価(外れ値やばらつきの検出)や、サンプリング手法の選定、結果の信頼区間算出など、統計的観点は様々な場面で役立ちます。また、統計量を事前計算しておきデータマートに入れておけばBI利用者が理解しやすくなることもあります。データマネジメントの一環としてデータ品質を数値で監視する場合も統計指標(分布のゆがみや期間ごとの推移等)を用います。要するに統計の知識は、データ基盤を活用して得られる数値の裏付けや信頼性評価を行う上で不可欠なのです。
実務での必要性: 実務では、データ分析やレポート作成の際に統計の知見が要求されます。例えば売上の傾向を議論する際、「平均値」だけでなく「分散」も示して波が大きいか小さいか説明したり、アンケート結果では「割合の差」が有意かどうかカイ二乗検定したりします。また機械学習の前提としてデータ分布や特徴量の相関を統計的に把握することも重要です。さらに経営層への説明では「この差は偶然ではないと言えるのか?」と問われるため、p値や信頼区間を用いて結果の有意性を説明します。統計に明るいエンジニアは、データからの主張に説得力を持たせられるため重宝されますskillupai.com。現代のデータ関連職には統計検定など資格取得を推奨する企業も多く、統計スキル向上はキャリアに直結すると言えるでしょう。
機械学習(ML)
概要: 機械学習(Machine Learning)はコンピュータに大量のデータを与えてデータ内のパターンを自動学習させる技術です。学習したモデルは未知のデータに対して予測や分類などの判断を行えるようになります。機械学習には大きく分けて「教師あり学習」(正解ラベル付きデータから分類・回帰モデルを学習)、「教師なし学習」(ラベルなしデータからクラスタリングなどパターン発見)、「強化学習」(試行錯誤により最適行動を学習)の3種類があります。代表的なアルゴリズムに、線形回帰・ロジスティック回帰、決定木・ランダムフォレスト、SVM、k-meansクラスタリング、ニューラルネットワークなどがあります。特にニューラルネットワークを多層化したディープラーニングは画像・音声・自然言語処理で革命をもたらしました。
データ基盤での位置づけ: データ基盤が十分に整備されデータが蓄積されると、その先の高度分析として機械学習が登場します。蓄えたビッグデータから顧客行動予測や需要予測モデルを構築したり、異常検知を行ったりと、データから価値を創出する手段が機械学習です。データエンジニアは機械学習エンジニアやデータサイエンティストと協働し、学習に適した特徴量データセットを準備したり、モデルの学習パイプラインを実装したりします。機械学習そのものの専門知識(アルゴリズムの数理やハイパーパラメータ調整など)はデータサイエンティスト領域ですが、エンジニアにも基本的な理解は必要です。例えばモデルが前提とするデータ分布や前処理の意味を知らないと、データ基盤から誤った入力を渡してしまう危険があります。
実務での必要性: 機械学習スキルは、データ分析を一歩進めて予測モデルや高度な自動化を実装する際に不可欠です。実務シーンでは、顧客の離反予測モデルを作ってマーケティング施策に活かす、工場センサーデータから故障予知を行う、画像から不良品を検出する、といったタスクがあります。それぞれに適したアルゴリズムを選び、十分なデータで学習させ、適切な評価指標で性能を測ります。そして精度を高めるため特徴量エンジニアリングを施し、必要ならアンサンブル学習なども検討します。こうしたモデル開発サイクルには試行錯誤が伴いますが、統計やプログラミング知識と合わせて機械学習の知見があると効率よく進められます。また実運用に耐えるモデルを作るには過学習対策や交差検証などのML実践テクニックも要ります。昨今はAutoMLなども出ていますが、基本原理を理解している技術者ほどチューニングやトラブル対応で成果を出しやすいです。
MLアプリケーション開発
概要: MLアプリケーション開発は、機械学習モデルを実際のソフトウェアシステムに組み込み、継続的に提供・運用するための開発手法です。モデル開発(Jupyter Notebook上での実験など)だけでなく、モデルをデプロイしてユーザが利用可能な形にする一連の工程(API化、スケーリング、モニタリング等)を含みますqiita.com。これはしばしばMLOps(Machine Learning Operations)と呼ばれ、Dev(開発)とOps(運用)を統合した文化・プラクティスですqiita.com。具体的には、モデルをDockerコンテナ化しクラウド上の推論サービスにデプロイ、負荷に応じて自動スケールし、またモデルの精度劣化を監視して再学習パイプラインを動かす…といった仕組みを作ります。
データ基盤での位置づけ: データ基盤から生まれた機械学習モデルは、MLアプリケーション開発を経て初めてエンドユーザに価値を提供します。例えば、データ基盤上で作成された需要予測モデルを社内の在庫管理システムに統合し、自動発注の判断材料に組み込む場合、モデルをREST APIとして公開しシステムから呼び出せるようにします。その際、データ基盤で整備された最新データを定期的にモデルにフィードし直し学習するパイプラインも動かすでしょう。このように、データ基盤(データの供給源)とモデル運用基盤(モデルを載せるアプリ部分)を繋ぐ役割がMLアプリ開発にはあります。データエンジニアがMLOpsエンジニアを兼ねて、基盤全体を構築するケースも増えてきました。
実務での必要性: 実務では、モデルを作って終わりではなく「どうユーザに届けるか」を考える必要があります。例えば小売業での購買予測モデルを作ったら、店舗スタッフが使えるタブレットアプリに予測結果を表示する、といった具合です。その実装では、モデルをエンドポイント化して推論結果をリアルタイム提供し、応答速度やサービスの高可用性にも気を配ります。またモデル再学習はバッチ処理としてデータ基盤上に組み込み、モデルリリースの自動化(CI/CD for ML)も検討します。加えて、モデルの予測精度や入力データ分布を継続監視し、異常があればアラートを出す体制も運用上重要です。これらはソフトウェアエンジニアリングとデータサイエンスのハイブリッドなスキル領域で、MLをビジネスに組み込むために不可欠です。昨今は各社でMLOpsプラットフォームやクラウドサービス(AWS SagemakerやGCP Vertex AIなど)が整いつつありますが、それらを使いこなすにも基礎となるMLアプリ開発スキルが求められています。
プロジェクト管理/開発プロセスとアーキテクチャ
プロジェクト管理/方法論/運用/アーキテクチャは、組織として「継続的に価値を出し続ける仕組み」です。適切な方法論とSRE的運用、将来を見据えたアーキ構成は、スケール時の「コスト」「信頼性」「変更容易性」を左右します。人・プロセス・技術を束ね、データ活用を「一度きりの成功」から「反復可能な制度」へ昇華させるレイヤです。
プロジェクト管理/マインド
概要: プロジェクトでの心得とは、チーム開発を円滑にしプロジェクトを成功に導くための態度・プラクティスです。技術スキルだけでなく、コミュニケーションやリスク管理、自己管理といったヒューマンスキルが含まれます。例えば進捗が見えるたびに報告・共有する、問題が起きたら早めにエスカレーションする、タスクの引き継ぎやドキュメンテーションを怠らない、などが基本的な心得です。また、自分だけしか分からない状態(属人化)を避け、誰かが欠けてもプロジェクトが滞らないようにする意識も重要です。「替えが利かない人」に頼りすぎない組織づくりが必要であり、個人依存のリスクを最小化しておくべきとされていますqiita.com。
データ基盤での位置づけ: データ基盤プロジェクトも他のソフトウェア開発プロジェクトと同様、チームで遂行されます。そこでは要件定義から設計・実装・テスト・リリース・運用までメンバー間の連携が不可欠です。データ基盤特有の難しさとして、関与部門が広範(IT部門だけでなく事業部や経営企画など)になりがちな点があります。そのためプロジェクトマネージャのみならず各エンジニアも、ビジネス部門との橋渡し役を担う場面がありますbrainpad.co.jp。このとき技術用語を噛み砕いて説明する、相手のニーズを丁寧に聞くといった姿勢が成果を左右します。またデータ分析プロジェクトは不確実性が高いため、柔軟な対応(アジャイルな姿勢)やスコープ管理の心得も重要です。全員がプロジェクトゴールを共有し、自律的かつ協調的に動くことがデータ基盤構築成功のカギとなります。
実務での必要性: 実務では、納期やリソースに制約がある中でプロジェクトを進めねばなりません。その際、メンバー各自が「何を優先すべきか」「チームのために自分ができることは何か」を考えて行動することが求められます。例えば、遅延しそうなタスクがあれば早めにリーダーに相談し、別メンバーと分担する提案をするqiita.com、レビュー待ちの間にドキュメント整備を進めて単価の高い人(リーダーやレビュア)の負担を減らすqiita.com、など主体的な動きができるとプロジェクト全体が円滑になります。逆に、個人の中だけで問題を抱え込んで報告しなかったり、属人化した状態で突然その人が離脱すると、大きなリスクとなりますqiita.com。したがって常にチーム全体を意識して情報共有と協力を行う姿勢が不可欠です。プロジェクト心得は一朝一夕には身につきませんが、意識的に実践と振り返りを重ねることで磨かれていくものです。
システム開発方法論
概要: 開発方法論とは、ソフトウェア開発プロジェクトを進める手順や管理手法の枠組みです。典型的な方法論にウォーターフォール型とアジャイル型があります。ウォーターフォール開発は要件定義→設計→実装→テスト→リリースの工程を順次進める手法で、初期に全機能の要求を確定し、工程ごとに担当者を分けて進めます。一方アジャイル開発は機能を小さく分割し、設計・実装・テストのサイクルを繰り返して徐々にシステムを完成させる手法です。スクラムやXPに代表され、要求変更への柔軟な対応や早期リリースによるフィードバック重視が特徴です。どちらの方法論にもメリット・デメリットがあり、プロジェクトの性質に応じて適切な手法を選択・組み合わせます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤プロジェクトでも開発方法論の選択は重要です。要件が明確で変更が少ない部分(例えば既存システムからのデータ移行など)はウォーターフォール的に計画しやすいでしょう。一方、データ分析の要求はやりながら変わることが多いため、ダッシュボード開発や機械学習PoCなどはアジャイル的な進め方が適しています。アジャイルではスプリント毎に使えるデータマートやレポートを少しずつリリースし、ユーザー部門からフィードバックをもらい改善します。これはデータ活用の現場に合致しており、現代のデータプロジェクトではアジャイル手法が主流になりつつあります。もっとも、会社によってはウォーターフォール型の厳密なプロジェクト管理(進捗報告様式やドキュメント作成)が求められるケースもあるため、双方の方法論を理解しハイブリッドに使えると理想的です。
実務での必要性: 実務のプロジェクト管理では、例えば短期間でまず動くデータパイプラインを作り、その後段階的に機能拡張する、といった進め方を取る場合があります。この際アジャイルの考え方(優先度の高い機能から実装し、動くものを見せて調整)が非常に有効です。また日々の開発でもデイリースクラムのようなスタンドアップミーティングを行い、チームの障害を早期に取り除く工夫が成果につながります。一方で要件凍結後の変更管理などウォーターフォールの知見も必要になる局面があります。結局のところ、大事なのは方法論に人が縛られるのではなく、プロジェクト目標達成のため適切に応用することです。開発方法論を知っていれば、計画の立て方やリスク管理、人月算出などプロジェクト運営全般に説得力を持たせられます。データエンジニアであっても、基本的な開発プロセスやアジャイル/Scrumの用語(プロダクトバックログやバーンダウンチャート等)を理解しておくとチーム内で円滑に動けるでしょう。
システム運用
概要: 運用とは、システムがリリースされた後に安定稼働させ続けるための活動全般を指します。システム監視、障害対応、パフォーマンスチューニング、定期メンテナンス、アップデート適用、利用者サポート、バックアップ取得とリストア訓練など、多岐にわたります。運用フェーズでは**「いかに早く問題を検知し復旧させるか」**や、問題そのものを未然に防ぐ仕組みづくりが重視されます。監視については、システムの各種メトリクス(CPU・メモリ使用率、処理時間、キューの長さ等)やログを集約し、しきい値を超えればアラート通知するような体制を構築します。DevOpsのカルチャーでは、開発(Dev)と運用(Ops)の連携を密にし、継続的な改善(Continuous Improvement)を図ります。
データ基盤での位置づけ: データ基盤は動き始めてからが本番です。日次バッチが予定通り成功しているか、遅延や失敗がないかを毎日確認するのも運用の仕事です。データの鮮度を保つためには、ジョブスケジューラやワークフロー(例: Airflow)の運用を適切に行い、万一失敗したらリトライや担当者への通知が行くようにします。また、データ基盤特有の運用としてデータ品質の監視があります。例えば昨日時点のデータ件数が平常時より極端に少ない/多い場合にアラートを上げる、数値項目の分布に乱れが出ていないか定期チェックする、といったものです。さらに権限管理運用(新入社員にアクセス権を付与・離職者を剥奪する等)や、データ容量管理(ストレージがいっぱいにならないよう古いデータのアーカイブ)も重要です。運用は、データ基盤というサービスを長期に安定提供するための守りのスキルと言えます。
実務での必要性: 実務では、24時間365日動かすべきバッチもあり得ます。例えばIoTセンサーデータをリアルタイムで集計するストリーミング基盤では、運用担当者が常にダッシュボードで処理遅延を監視し、異常が出たら即座に対応する体制を敷くでしょう。運用スキルとして、Linuxコマンドでプロセスの生死を確認・再起動する、SQLで不整合データを手当てする、などの場当たり対応力も求められます。また障害発生時のオンコール体制(誰が連絡を受けて対処するか)を決め、手順書を整備しておくのも運用の一環です。さらに、運用負荷自体を軽減するために自動化スクリプトを書いたり、Terraform等でインフラ復旧をスムーズにしたりといった改善も行います。データエンジニアは開発段階から運用を意識し、「後で運用しやすい設計」(例: ログ出力の充実やリトライ機構の組み込み)を心がける必要があります。運用フェーズまで目配りできるエンジニアは、システム全体のライフサイクルを見通せる頼もしい存在です。
アーキテクチャー論
概要: アーキテクチャー論とは、システムの構造設計や構成要素のパターンに関する知識体系です。どのようなコンポーネントでシステムを構成し、それらをどう組み合わせれば要求を満たすか、という高レベル設計の指針となります。基本的なアーキテクチャ原則として関心の分離(Separation of Concerns)がよく挙げられ、これはソフトウェアを役割ごとに分離することで理解と保守を容易にする考え方です。またアーキテクチャ設計では、可用性・スケーラビリティ・パフォーマンス・セキュリティ・保守性・コストといった非機能要件のバランスを取ることが求められますissoh.co.jp。代表的なシステムアーキテクチャパターンに、レイヤードアーキテクチャ(プレゼンテーション層・ドメイン層・インフラ層などに分ける)、クライアントサーバ、マイクロサービス、イベント駆動、サーバレスなどがあります。アーキテクチャー論は、それぞれのパターンの利点・欠点や適用場面の知見を蓄積したものと言えます。
データ基盤での位置づけ: データ基盤も一種のシステムですから、その全体構成を設計する際にアーキテクチャ思考が必要です。例えば「生データの蓄積層・加工処理層・提供層」に分離するレイヤードアーキテクチャを適用したり、バッチ処理部分とAPI提供部分をマイクロサービス的に独立させてスケールやすくしたりといった判断があります。さらに、データ基盤は周辺システムとの連携も多いので、イベント駆動型(データ発生をトリガーに処理を進める)にするかスケジュール駆動にするか、といった選択も設計段階で行います。適切なアーキテクチャを選択・組み合わせることで、システム全体の柔軟性や拡張性が大きく左右されますissoh.co.jpissoh.co.jp。データ基盤では特に、「スケーラビリティ(データ量増大に耐える)」「モジュール性(新しいデータソース追加が容易)」が重要になるため、それらを満たすアーキテクチャパターンを採用することが成功のポイントとなります。
実務での必要性: 実務でエンジニアがアーキテクチャ設計に関わる場面として、新規システム立ち上げや既存システム刷新時があります。その際、要求を分析し適切な構成を提案できると非常に価値が高いです。例えば、「リアルタイム性が要求されるのでバッチではなくストリーム処理基盤+イベント駆動で作りましょう」「データ件数が将来膨大になるのでスケーラブルなクラウドデータウェアハウスを採用しましょう」「可用性重視なので各コンポーネントは冗長化しましょう」といった具合です。アーキテクチャ知識が豊富なエンジニアは、様々な選択肢のトレードオフを説明しながら最良の道を示せます。またコードを書く際もSOLID原則など設計原則を意識することでシステムの頑健性が増します。システム全体を俯瞰して性能・信頼性・保守性を高めるのがアーキテクトの役割であり、データエンジニアもこの視点を持つことで技術リードやCTO的ポジションへキャリアを広げることが可能です。