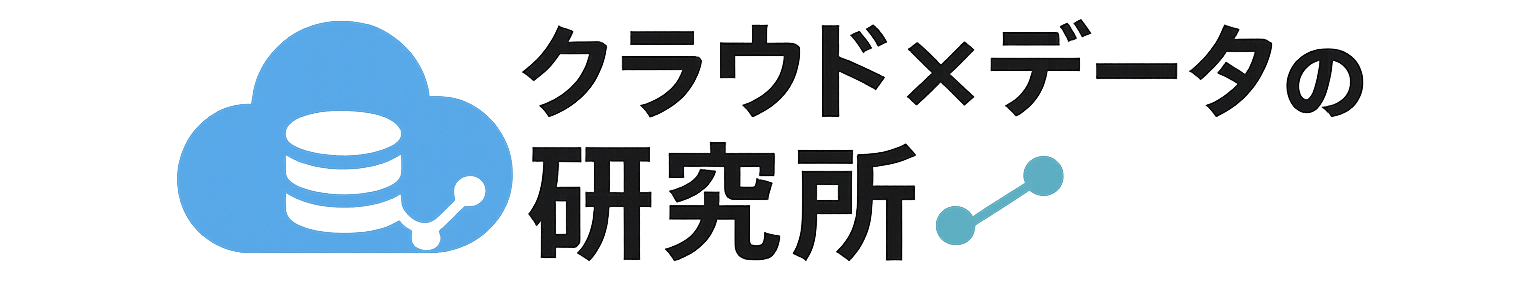Table of Contents
そもそも分散処理とは?
近年のデータ分析では、1 台のコンピュータでは扱いきれない膨大なデータを処理する必要があります。
そこで登場するのが 分散処理 です。これは「大量のデータを複数のコンピュータに分散して並列処理する仕組み」のことを指します。
イメージとしては、1 人で 1 万枚の書類を処理するのではなく、100 人で 100 枚ずつ分担して作業するようなものです。分散処理の目的は以下の通りです。
- 高速化:処理を並列化して短時間で分析を完了できる
- 拡張性:必要に応じてノードを増やすことで、処理能力をスケールアウトできる
- 耐障害性:一部のノードが故障しても全体の処理が継続できる

分散処理を支えるコンポーネント
分散処理基盤は複数のコンポーネントで構成されます。主要な役割をわかりやすく整理すると以下の通りです。
計算ノード(スレーブノード)
実際にデータを処理する役割を担う。PySpark でいう Executor、Snowflake でいう仮想ウェアハウスに相当します。MapRuduceの処理もこちらの計算ノードで実施する。
マスターノード(Driver / Coordinator)
処理の計画を立て、各ノードにタスクを割り当てる。Spark では Driver、Snowflake ではクエリオプティマイザが該当。
分散ストレージ
データを保存・分割して管理する。HDFS(Hadoop Distributed File System)、クラウドストレージ(S3、GCS)などが利用される。 ネットワーク ノード間の通信を制御し、データをやり取りする基盤。性能や信頼性に大きな影響を与える。

代表的なミドルウェアと技術
分散処理の代表格は以下のようなものです。
Hadoop
MapReduce 分散処理の草分け的存在。データを「Map(分割)」と「Reduce(集約)」の二段階で処理する仕組み。シンプルだが柔軟性に欠け、現在は徐々に役割を終えつつある。


Apache Spark
Hadoop の後継として広く使われる。メモリ上で処理を行うため高速で、バッチ処理からストリーミング、機械学習まで対応可能。PySpark は Spark を Python から利用できる APIである。
Snowflake (snowpark)
クラウド特化型のデータウェアハウス。ユーザーが意識しなくても裏側で分散処理が行われる。データフレームを扱うような感覚で SQL を投げると、自動で最適化・並列処理が実行される。
snowflakeには「snowpark」と呼ばれる「snowflakeを使い慣れた言語で使うためのAPIフレームワーク」が提供されています。
Presto / Trino
分散 SQL クエリエンジン。データをコピーせずに複数ストレージにまたがるデータを分析できる。
最近の技術傾向
ここ数年の分散処理技術にはいくつかの大きな流れがあります。
クラウドネイティブ化
Snowflake や BigQuery のように、ユーザーがクラスタ構築を意識しなくてもよいマネージドサービスが主流になっている。インフラ運用の負担が減り、分析に集中できます。
サーバレス化
処理リソースを自動でスケーリングし、利用した分だけ課金する仕組み。データサイズの増減に柔軟に対応できる。
データフレーム API の普及
PySpark や Pandas-like API、Snowpark など、プログラマが馴染みやすいインターフェースで分散処理を扱えるようになっている。SQL と Python 双方で操作できる点がポイント。 ストリーミングとバッチの融合 かつては「バッチ処理(大量データを一括処理)」と「ストリーミング処理(リアルタイム分析)」が分かれていたが、近年は両者を統合して扱える基盤(Spark Structured Streaming など)が増えている。
まとめ
分散処理は「大量データを複数ノードで並列処理する仕組み」であり、データ分析基盤の根幹を支える技術です。Hadoop から Spark、さらに Snowflake や BigQuery などのクラウド型サービスへと進化し、ユーザーは分散処理の複雑さを意識せずに分析できるようになりました。
今後も クラウド・サーバーレス・データフレーム API がキーワードとなり、データ分析の効率性がスタンダードになる流れになると私は考えています。