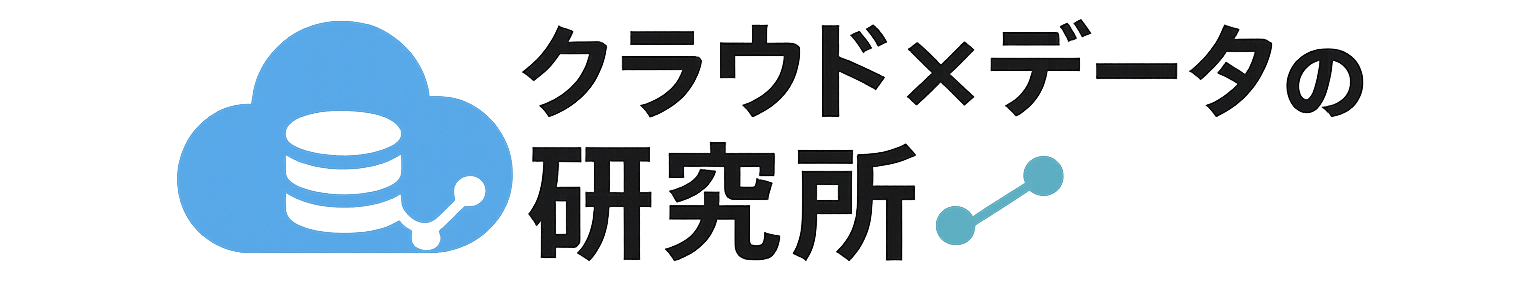みなさんも使用される機会が多くなったChatGPT――
私自身も使用しない日はもうありません。検索、文章要約、文章作成、画像作成・・・などなどほぼAIによる生成機能と生活を共にしています。
そんな中、GPTのユーザインターフェースには「エージェントモード」や「DeepResearch」機能などいくつか機能がありますね。
AIの進化は「単に質問に答える」段階から、「自ら考え、調べ、行動する」段階へと移行しています。

今回は、ChatGPT(GPT-5)に搭載されつつある新機能――AIエージェントモードやDeep Research、より長く思考するモード――がどのように動作し、何が変わるのかを解説します。

Table of Contents
AIエージェントモードとは?
従来のChatGPTは、ユーザーの質問に対してその場限りの回答を返す「受け身型」でした。
しかしエージェントモードは、あらかじめ定義されたゴールに向かってAI自身がステップを計画し、必要に応じて外部ツールやAPIを呼び出しながら作業を進める「能動型」AIです。
仕組み
- 目標設定
ユーザーが「〇〇を調べて資料を作って」と指示すると、AIが「最終成果物」を理解します。 - タスク分解
ゴール達成のためのステップ(検索 → 分析 → まとめ → 形式化)を自動生成。 - ツール利用
内部でWeb検索、計算ツール、コード実行、ファイル操作などを必要に応じて呼び出し。 - 自己評価と修正
途中結果を評価し、必要があれば別ルートで再試行。 - 最終納品
ゴールに沿った形で成果を出力(文章、表、コード、レポートなど)。
利用例
利用例としては下記のようなものがあります。
- 長期的な市場調査(複数ソースのクロスチェック付き)
- 複雑なデータ分析 → グラフ化 → PDFレポート出力
- Webサイト構築やアプリ開発のプロトタイプ生成
実際に、あるURLをインプットにして「このサイトの記事を要約してサマライズしてほしい」とエージェントモードで実施をすると下記のようにChatGPT自体が何度も自身で思考をしてアウトプットを作成することがわかります。

Deep Researchとは?
Deep Researchは単なるWeb検索ではありません。「AIが複数の検索・要約・比較プロセスを自動で繰り返し、根拠付きの情報を提示する」モードです。
特徴
特徴としては下記があげられます。
- 多段階探索:一度の検索で終わらず、関連するキーワードや角度を変えて再検索
- 情報統合:複数の情報源を要約・照合し、一貫性を確認
- 出典表示:引用元URLを添付して透明性を担保
- 更新性重視:最新情報を優先的に抽出(時系列フィルタ)
利用例
利用例としても、学術研究の先行調査などに利用することも可能です。
- 学術研究の先行調査
- 最新ニュースや法改正の詳細確認
- 特定分野の比較レビュー記事作成
より長く思考するモード(Longer Reasoning)
このモードでは、AIが1回の回答生成の中で使える「推論トークン数」や「ステップ数」を増加させ、より深い分析・長期的な計画立案を可能にします。
通常モードとの違い
- 通常:限られた思考時間で最も合理的な答えを素早く提示
- 長時間モード:途中で仮説検証や再計算を行いながら、より精度の高い答えを導出
利用例
- 数十ステップに及ぶ複雑な数学的証明
- 長期的な事業計画やシナリオ分析
- 複雑なプログラムのアルゴリズム設計
他の関連機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| あらゆる学びをサポート | 教材作成・演習問題生成・フィードバックなど、学習プロセスを包括的に支援 |
| 画像を作成する | テキストからAI画像を生成(プレゼン資料やサムネイル制作に有用) |
| ウェブ検索 | 瞬時の情報取得に特化(Deep Researchほど多段階ではない) |