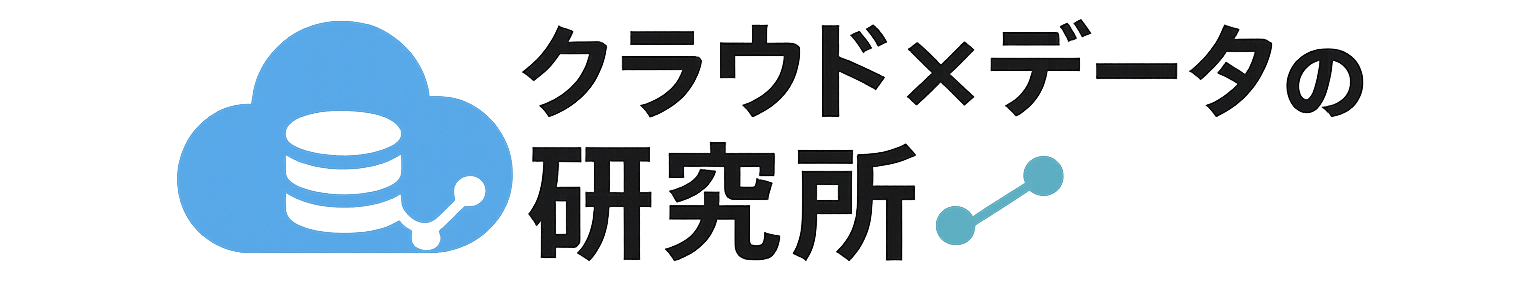こんばんわ!データクラウド研究所です!
データ分析やAIの現場では「データレイク」や「データウェアハウス」といった言葉をよく耳にします。最近はその進化形として「レイクハウス」という考え方が広がり、その中で重要な役割を果たしているのが オープンテーブルフォーマット です。
Table of Contents
データってどこに置いてるの?
企業やサービスでは、毎日のように大量のデータが生まれています。
例えば:
- ネットショップの購入履歴
- スマホアプリの利用ログ
- 写真や動画などのファイル
こうしたデータはよく クラウドの「オブジェクトストレージ」(例:Amazon S3、Google Cloud Storageなど)に保存されます。
でも、そのままではただのファイルの集まり。SQLで分析したり、AIの学習に使ったりするには「表(テーブル)」の形に整える必要があります。
そこで登場する「オープンテーブル形式」
オープンテーブル形式(Open Table Format)とは、オブジェクトストレージにあるデータを「データベースのテーブルっぽく扱えるようにする仕組み」です。
つまり、ファイルの寄せ集めを「ちゃんとしたテーブル」として見せてくれるルールや規格のこと。

代表的なものに
- Delta Lake(Databricks発)
- Apache Iceberg(Netflix発、Apacheプロジェクト)
- Apache Hudi(Uber発、Apacheプロジェクト)
があります。
なんで「オープン」なの?
ここでいう「オープン」とは:
- 仕様が公開されている → 誰でも自由に実装・利用できる
- オープンソースで開発されている → コミュニティが改良や機能追加を続けている
- いろんなエンジンから使える → Spark、Flink、Trino、Prestoなど複数のツールが同じ形式を読める
要するに「特定ベンダーに縛られず、どんなツールでも同じデータを扱える共通フォーマット」なんです。
イメージでいうと、「USBメモリ」のようなもの。
どんなパソコンでもUSBポートがあれば読み書きできるのと同じで、オープンテーブル形式ならツールを選ばずにデータを読み書きできます。
何ができるようになるの?
オープンテーブル形式を使うと、ただの「ファイル置き場」だったデータレイクが、一気に便利になります。
- ACIDトランザクション
データを途中で壊さず、安全に更新できる(銀行の送金のように確実に記録されるイメージ)。 - スキーマ進化
列を追加・削除してもテーブル全体を作り直さなくてよい。 - タイムトラベル
過去の状態に戻って分析できる。昨日時点のデータを再現、など。 - バッチ処理とストリーミング処理の両立
まとめて処理するのも、リアルタイムで処理するのも両方OK。
レイクハウスとの関係
最近よく聞く「レイクハウス」は、データウェアハウス(DWH)の便利さとデータレイクの柔軟さを組み合わせた新しいアーキテクチャです。
この「レイクハウス」の基盤を支えているのが、まさに オープンテーブル形式 です。
まとめ
- オープンテーブル形式は、データをオブジェクトストレージ上に「テーブル」として扱える共通ルール。
- Delta Lake、Apache Iceberg、Apache Hudi などが代表例。
- ベンダーロックインを避け、複数ツールから同じデータを使えるのが大きなメリット。
- レイクハウスの実現に欠かせない要素。
一言で言うと:
「USBのように、どんな分析エンジンでも共通で使えるテーブル規格」
と覚えるとイメージしやすいです。