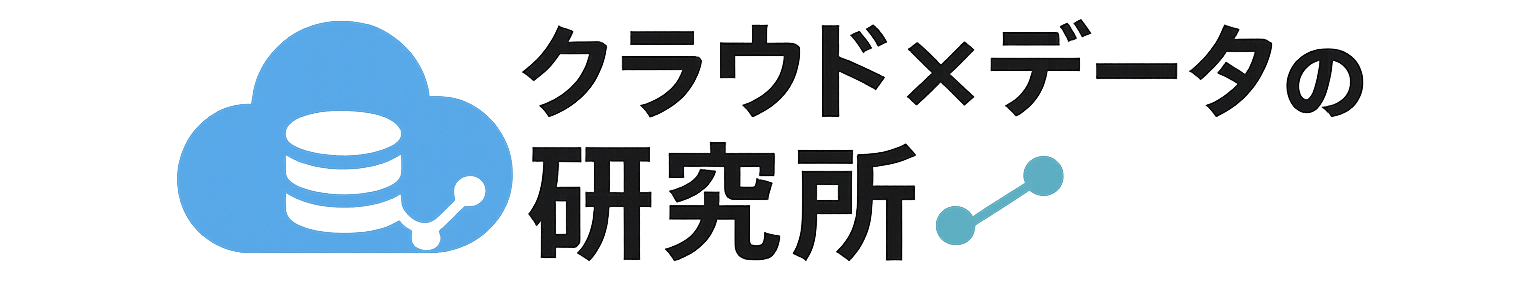こんにちは、データクラウドです!
今回は「エンジニアにこそ必要な会計感覚」についてわかりやすく解説します。
「会計なんて経理やマネージャーがやることでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが、実はプロジェクトの成功やエンジニア自身の評価に直結する大切な要素です。クラウド費用や人件費といった身近なコストを切り口に、商売感覚を身につけるための第一歩を見ていきましょう。
Table of Contents
エンジニアにこそ必要な「会計感覚」と「商売感覚」
エンジニアとして日々システムを設計・構築していると、つい「技術的に正しいかどうか」だけに目が行きがちです。もちろんそれは大切な視点ですが、実はプロジェクトの現場ではもうひとつ重要な要素があります。それが 「お金の感覚」=会計やコストの視点 です。
なぜかというと、どんなに優れた技術であっても「お金を払って採算が合う」ものでなければ導入されません。ビジネスは「投資して、利益を出す」活動です。
なぜエンジニアに会計感覚が必要か
「技術的に最適」な答えが「ビジネス的に最適」とは限りません。
例えば、高価なサーバを導入すれば性能問題は一気に解決できるかもしれません。しかし、その投資額を回収できるだけの利益が生まれなければ、ビジネス的には赤字です。
逆に、少し工夫してクラウドのスケーリング設定を見直すだけで問題を解決できれば、追加コストはほとんどかかりません。顧客から見れば「技術的に十分かつ費用が抑えられる」提案の方が何倍も価値があるのです。
つまり、エンジニアにとっての「正解」は、技術だけでなく 「コストと利益を踏まえた正解」 であるべきなのです。
BSとPLをざっくり理解する
会計には様々な仕組みがありますが、エンジニアがまず押さえるべきは BS(バランスシート)とPL(損益計算書) です。
- BS(バランスシート)=会社の体力
会社が持っている資産や負債をまとめた表。貯金と借金の関係を示します。 - PL(損益計算書)=会社の成績表
売上から費用を引いて、どれだけ利益が出たかを示します。
プロジェクトに関わる私たちに直結するのは「費用」と「利益」の部分です。つまり「人を何時間動かしたか」「クラウドにどれだけ課金したか」がそのままPLの費用として計上されます。
ITプロジェクトで意識すべきコスト
では、エンジニアが日常で意識すべき「費用」とは何でしょうか?代表的なのは次の3つです。
- クラウド費用
AWSやGCPなどのクラウドは「従量課金モデル」。リソースを立ち上げっぱなしにすると、そのままコストが膨らみます。性能要件を満たしつつ、無駄なインスタンスを削るのも立派な会計感覚です。 - 人件費
プロジェクトの最大コストは「人の時間」です。余計な作業、やり直し、属人化はすべて赤字要因。効率的な設計や自動化は、そのまま「利益を守る行為」になります。 - ライセンス・サブスクリプション費用
ソフトウェアの利用料や月額課金は、積み重なると大きな固定費に。導入前に「長期的に本当に必要か」を見極めるのも重要です。
会計感覚があるエンジニアとないエンジニア
ここで2つのストーリーを想像してみてください。
- エンジニアA:「高性能サーバを入れれば問題は解決します!」
→ 顧客:「コストが高すぎて無理です」 - エンジニアB:「現状のクラウド環境を見直せば十分解決できます。追加投資は不要です」
→ 顧客:「それなら助かります!」
どちらが「頼れるエンジニア」と見られるかは明らかです。会計感覚を持って提案できるかどうかが、信頼を得られるかどうかの分かれ道になるのです。
まとめ:技術×商売感覚がプロジェクト成功のカギ
エンジニアにとっての会計感覚とは、「技術をお金に置き換えて考える力」です。クラウド費用、人件費といった身近なコストを意識しながら提案できれば、顧客やマネジメントからの信頼は格段に上がります。
技術力に加えて数字を意識できるエンジニアは、単なる「技術屋」ではなく「ビジネスを動かす存在」になれます。これがキャリアを広げる第一歩です。