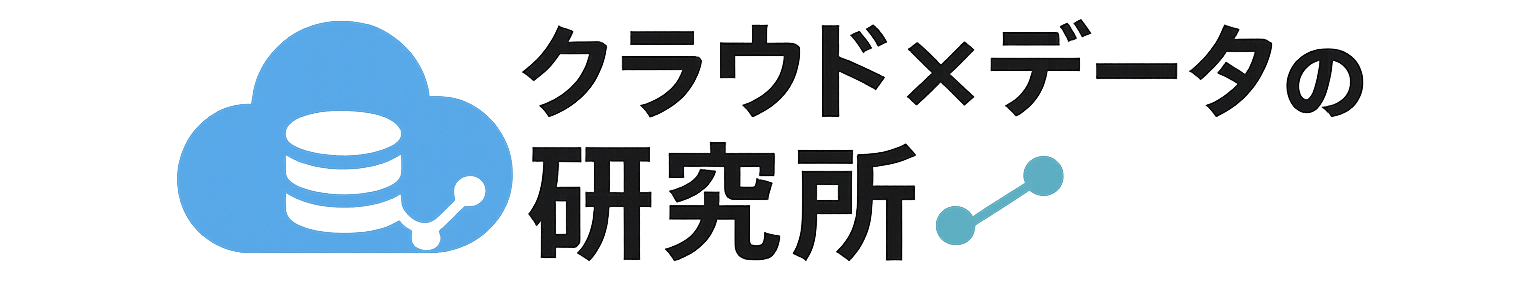Table of Contents
PySparkとは?
PySpark(パイスパーク)とは、分散処理エンジン 「Apache Spark をPythonから利用できるライブラリ」です。SparkはJavaやScalaで開発されていますが、データ分析分野ではPythonが広く使われているため、多くのデータサイエンティストやエンジニアがPythonでSparkの機能を利用できるようにしたのがPySparkです。
Pythonユーザーにとっては「大規模データを扱うための分散処理基盤」と「おなじみのPython文法」が組み合わさった非常に強力なツールといえます。
Apach Sparkの記事はこちらで分かりやすくご説明しています!
PySparkの特徴とメリット
1. Pythonユーザーに優しいAPI
PySparkはPandasに似た「DataFrame API」を備えており、行や列を指定してデータを操作したり、集計やフィルタリングを直感的に記述できます。これにより、普段Pythonでデータ分析をしている人でも比較的スムーズにSparkの分散処理を利用できます。
2. 大規模データの処理を簡単に
通常のPythonではメモリに収まらない巨大なデータを扱うのは難しいですが、PySparkを使えば複数のノードにデータを分散して処理できるため、数百GB〜TB級のデータでも扱えます。
3. 機械学習やSQLとの統合
PySparkはSpark MLlib(機械学習ライブラリ)やSpark SQLと統合されているため、データの前処理から学習モデルの構築、SQLによる集計まで一貫して処理できます。Pythonだけで完結できるのは大きな魅力です。
PySparkの基本的なコード例
例えば、CSVファイルを読み込み、平均値を計算する処理は以下のように書くことができます。
from pyspark.sql import SparkSession
# SparkSessionの作成
spark = SparkSession.builder.appName("example").getOrCreate()
# CSVデータを読み込み
df = spark.read.csv("data.csv", header=True, inferSchema=True)
# 特定カラムの平均値を計算
df.groupBy("category").avg("value").show()一見するとPandasに似ていますが、このコードは実際には分散環境で並列処理されるため、大規模データも効率的に処理できます。
PySparkが使われるシーン
- ログ分析:Webアクセスログやアプリ利用ログを分散処理して傾向を把握する。
- ETL処理:大量のデータを抽出・変換・ロードするバッチ処理。
- 機械学習の前処理:数百万件以上の特徴量データを効率よく加工。
- リアルタイム処理:Spark Streamingを使ってストリームデータを扱うケース。
クラウドサービスでの利用例
クラウド環境では、PySparkはマネージドサービスを通じて簡単に利用できます。
- AWS EMR(Elastic MapReduce)
Sparkクラスタを簡単に構築し、PySparkを利用可能。S3との連携もスムーズ。 - Azure Synapse / Databricks
DatabricksはSparkをベースとしたサービスで、ノートブック上でPySparkを直感的に利用可能。 - Google Cloud Dataproc
SparkクラスタをGCP上でマネージド管理。BigQueryやGCSと連携してデータ処理。
Spark(Scala/Java)とPySparkの違い
Spark本体はScalaで動いているため、Scala版の方がネイティブに高速ですが、PySparkはその利便性から圧倒的にユーザー数が多いです。
特に、Pythonエコシステム(NumPy、Pandas、scikit-learnなど)と連携しやすい点がPySparkの大きな強みといえます。
まとめ
PySparkは、Apache Sparkのパワフルな分散処理をPythonで直感的に扱えるライブラリです。
Pandasのような使いやすいAPIを持ちながら、TB級のデータを分散処理でき、クラウドサービスとも親和性が高いため、現代のデータ分析基盤では欠かせない存在になっています。
次の記事では、このPySparkと並んで注目されている「Snowflake」について取り上げ、クラウド時代の分散処理基盤の特徴やSparkとの違いを解説していきます。