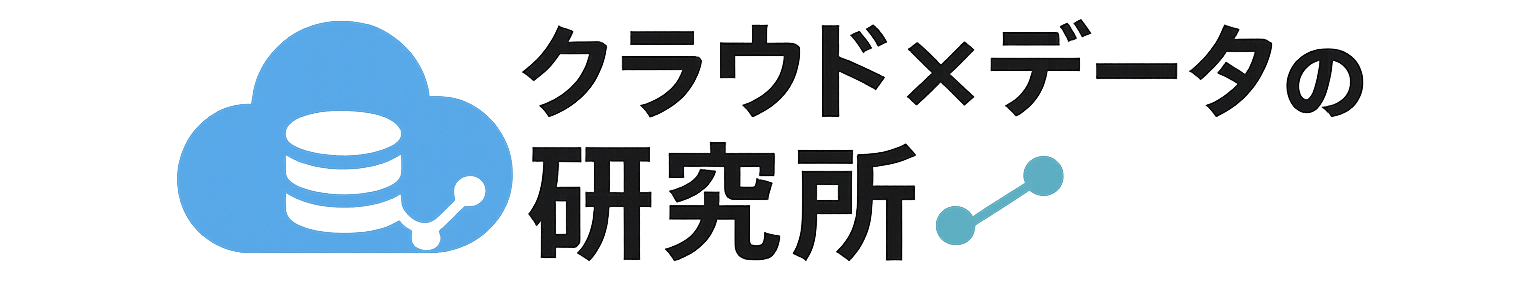まず、「キュー」あるいは 「データスキュー (data skew)」という言葉は、分散処理システム(Spark/Databricks 等)でしばしば問題になる現象を指します。
データスキューを解決するための代表的な方法がいくつか存在しますので、それぞれの対応内容を簡単にみていきましょう!
Table of Contents
データスキューの定義と問題点
- Spark や Databricks では、大量データを複数のパーティションに分散して並列処理を行います。
- しかし、あるキー(たとえば
user_id、customer_idなど)にデータが極端に集中していると、そのキーを扱うパーティションだけ負荷が偏ります。 - この偏りが「データスキュー」です。
- スキューが起きると、その重いパーティションを処理するタスクだけが遅くなり、全体のジョブ完了時間を引き延ばす、あるいはメモリ不足で処理が失敗することもあります。
- Spark UI で「タスク間の処理時間のばらつき」「スパークステージにおける一部タスクの極端な遅さ」が見られることが典型兆候です。
- 特に、ジョイン や 集約 (groupBy / reduce) など、データをシャッフル再配置する操作で顕著に表れます。
つまり、スキュー = 分散処理が “負荷バランスを失った状態” と捉えるとわかりやすいです。
スキューを緩和する代表的な手法
以下の 3 つと、補足として Broadcast(ブロードキャスト)について整理します。
1. Salting(ソルト処理・プレフィックス付与)
概要
スキューを引き起こしているキーにランダムな「塩 (salt)」を付与し、元のキーを複数バリエーションに分散させて別のパーティションへ散らす方法です。 saturncloud.io+2Medium+2
実装の流れ(例)
- スキューキー(例:
user_id= “power_user”)を特定 - そのキーの値に対して、乱数を付与して
user_id_0,user_id_1… のように複数に振り分け - 対応する結合側データ(プロファイル側など)にも同じルールで salt を付与
- ジョインを行い、結合後に salt を取り除く/集約し直す
注意点・限界
- salt を付与するバリエーション数(塩の数)が少なすぎると効果が薄い
- salt を付与しすぎるとオーバーヘッドになる
- Spark のデフォルトハッシュ方式と salt が衝突するケースもあり、必ずしも万能とは言えない Reddit+1
- salt 処理/逆変換処理が必要なので実装がやや煩雑
Salting は「ホットキーを意図的に分散させる」アプローチの典型例です。
2. 再パーティション (Repartition)
概要repartition() や repartitionByRange() などを使って、パーティション数を増やしたり、分散方法(ソート範囲など)を変えたりして、データの偏りを緩和する手法です。
利点
- パーティション数を増やすことで、処理をより多くのタスクに分散できる
- 並列度を上げられる
制約・限界
- 単にパーティション数を増やすだけでは、スキューキー自体の偏りは解消されない
- 再パーティション自体もシャッフルを伴うためコストがかかる
- 適切なパーティション数設定(CPU数、データ量)を見極める必要がある
Spark/Databricks では、/*+ REPARTITION */ のようなヒント句も使えます。
3. Skewed Keys の分離処理(ホットキー分割・個別処理)
概要
スキューを引き起こす “頻出キー(ホットキー)” をあらかじめ抽出し、それらを別ジョブや別処理パスで扱う方法です。
実装例
- スキューキーを抽出(例:
user_id = 12345が極端に多い) - そのキーに該当するレコードを別の DataFrame / ジョブに切り出す
- 残りのデータを通常ルートで処理
- 最後に両者をマージ/結合結果を統合
メリット
- ホットキーがジョイン処理全体に与える影響を最小化できる
- ホットキー処理に特化したリソース配分や最適化が可能
注意点
- 分離処理のロジック設計が必要
- キー判定基準が変動するデータでは維持コストがかかる
ブロードキャスト (Broadcast) について
概要
小さいテーブル(ルックアップテーブルなど)をすべての executor ノードに配布し、シャッフル(ネットワーク通信)なしに結合を行う方式です。
仕組み
- 結合側の片方をすべてのノードにキャッシュ的に配布
- 各 executor はローカルにその結合先テーブルを持つため、結合時にデータ移動を最小化できる
使うべき場面
- 片方のテーブルが非常に小さい(例:マスタ参照テーブル、コードマスタなど)
- 大規模テーブルとの結合で shuffle を回避したいとき
制約・注意点
- ブロードキャスト先のテーブルが大きすぎると、各 executor のメモリを圧迫
- ブロードキャストしてもスキューキー自体の偏りは解消しない
- スキューキーをブロードキャストしても、重い処理は避けられない
実際、問題文で「スキューキーをブロードキャストする」は不適切な対策とされています。
まとめ:対策の選択と使い分け
| 手法 | 用途 / 強み | 制約・注意点 |
|---|---|---|
| Salting | 偏ったキーを複数に分散、スキュー軽減 | Salt設計・逆変換が必要、衝突リスク |
| Repartition | 並列性を上げる/細分化 | 偏りそのものは解消しない、追加シャッフル |
| スキューキー分離処理 | ホットキーを隔離して影響を抑える | ロジック設計・動的キー変動に注意 |
| Broadcast | 小さい参照テーブルを結合時に配布して shuffle 避け | 大きすぎるとメモリ圧迫、スキューは解消不可 |
たとえば、クリックストリーム + ユーザープロファイル結合という文脈では:
- プロファイルテーブルが非常に小さいなら Broadcast Join を使って結合を避けることもできる
- ただし今回の問題では、「ブロードキャストをスキューキーに対して使う」は誤り
- よって、Salting や再パーティション、スキューキーの分離処理 を組み合わせて使うのが現実的な対策
Spark/Databricks では Adaptive Query Execution(AQE) がスキューの自動補正を支援する機能もありますが、完全ではなく手動対策を併用すべきです。